子どもと学ぶゴルフ×自然の関係 川崎市民開放日をレポート
草木の揺れる音、どこかから聴こえる鳥のさえずり、ふいに感じる花の甘い香り。そんな里山の自然と爽やかな芝の緑に包まれて過ごす時間は、私たちの心と体をリフレッシュさせてくれるでしょう。
今回訪れた「川崎国際生田緑地ゴルフ場」では、初心者でも無料で楽しくゴルフ体験ができる「ジュニアレッスン会」が毎年開催されています。今年はさらに「自然観察指導員と巡る ネイチャーウォッチング」が加わり、普段は見ることができないゴルフ場の自然も楽しめるプログラムとなりました。
そんな当日のイベントの様子をレポートするとともに、日本自然保護協会に所属する自然観察指導員の原田和樹さん、ゴルフ場支配人の菊田哲治さんにインタビュー。ネイチャーウォッチングの楽しみ方や「川崎国際生田緑地ゴルフ場」で長年続くサステナブルな取り組みをご紹介します。
川崎国際生田緑地ゴルフ場 支配人
菊田哲治
2007年入社、那須国際カントリークラブ、鶴舞カントリー倶楽部、サミットゴルフクラブを経て2024年4月より現在の川崎国際生田緑地ゴルフ場に着任。
2007年入社、那須国際カントリークラブ、鶴舞カントリー倶楽部、サミットゴルフクラブを経て2024年4月より現在の川崎国際生田緑地ゴルフ場に着任。
公益財団法人 日本自然保護協会 自然のちから推進部 企業連携チーム 主任
原田和樹
学生時代は社会学を専攻。その後メーカーで5年半営業に従事。学生時代から社会人初めは自然とほとんど接点のない生活を送っていたが、自然は好きだったことから、自然に関する仕事に興味を持ち、日本自然保護協会へ転職。現在は、営業時代の経験を活かしながら企業の皆さまと自然保護を推進。具体的には寄付のお願い、連携企画の検討、セミナー対応、自治体×企業×NGOの推進などを行っている。
学生時代は社会学を専攻。その後メーカーで5年半営業に従事。学生時代から社会人初めは自然とほとんど接点のない生活を送っていたが、自然は好きだったことから、自然に関する仕事に興味を持ち、日本自然保護協会へ転職。現在は、営業時代の経験を活かしながら企業の皆さまと自然保護を推進。具体的には寄付のお願い、連携企画の検討、セミナー対応、自治体×企業×NGOの推進などを行っている。
都心部にある豊かな緑地「川崎国際生田緑地ゴルフ場」で地域市民向けのイベントが開催
小田急線の向ヶ丘遊園駅からバスで5分ほどの場所にある「川崎国際生田緑地ゴルフ場」。コース設計の名匠・井上誠一氏が手がけた都市近辺のゴルフ場として知られ、1952年の開場以来、多摩丘陵の自然を活かしたコースが多くのゴルファーを魅了し続けています。
このゴルフ場は地域の人から「川国(かわこく)」の愛称で親しまれています。毎年夏と冬には市民開放日があり、普段はプレーヤーしか入れないゴルフ場の一部を開放して、市民のためにさまざまなイベントを開催。近隣住民も、ゴルフ場の豊かな自然を楽しめる仕組みがあるのです。

なかでも「ゴルフ・ジュニアレッスン会」は、今年で17回目となる人気イベント。子どもたちの健全な身体づくりとゴルフの楽しさを伝えるとともに、ゴルフで培われるフェアプレーの精神や忍耐力を育てることにつなげる目的で開催されています。
今年の冬の市民開放日は「川国で遊ぼう 2025 冬」と称し、ゴルフ場の動物や植物を観察する「自然観察指導員と巡るネイチャーウォッチング」が初めてプログラムに組み込まれ、10名の小学生とその保護者が参加しました。

開会式では、公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟 ジュニアゴルファー育成委員会 委員長の服部さまからご挨拶をいただきました。当日は朝から雨模様でしたが、「ゴルフは自然とたたかうスポーツだといわれています。今日のような天気だからこそ得られる発見を、ぜひ楽しんでください」と温かい言葉が贈られ、イベントがスタート。

まずは公益財団法人 日本自然保護協会の自然観察指導員の方々が案内するネイチャーウォッチングです。ゴルフ場の自然を観察するにあたり、最初に自然観察指導員の原田さんから簡単なレクチャーが行われました。
原田さん
このゴルフ場は、高度経済成長期に失われた里山の環境が残っている大切な場所です。特に3つのポイントで、多くの生き物にとってかけがえのない場所になっています。
1つめは、都市の住宅街に比較的大きな自然が広がっていること。2つめは、継続して人の手を入れることで生態系のバランスを保っていること。そして3つめは、人があまり出入りしない時間帯があることです。
そのためこのゴルフ場には、タヌキや絶滅危惧種のホトケドジョウなど、里山の生き物が暮らしています。そして今日のような寒い時期や雨の日でも、自然観察をしてみると、さまざまな発見があるはずです。

「ツツピー」は何の鳴き声?
そして一行は外へ移動。自然観察指導員のメンバーが自己紹介をし、ゴルフ場にいる生き物のヒントが描かれたカードを片手に、観察を始めていきます。

最初に発見したのは、高木の幹に取りつけられた小さな巣箱。頬の部分が白く、お腹に黒い線のような模様が入ったシジュウカラという鳥のためにつくられました。巣箱の下から植物のクズや苔などが出ており、これは子育てをした跡なのだとか。

シジュウカラの鳴き声は「ツツピーツツピー」と表現されるそう。指導員の方の「鳥の鳴き声にも耳を傾けてみて」との言葉に促され意識してみると、いろいろな鳥の声が聴こえてきます。

バンカーの部分では、動物の足跡を発見。「これはタヌキかな?」「何匹通ったんだろう?」と想像をめぐらせました。

ゴルフ場の端に咲いていた椿の花びらをよく見ると、小さな黒い跡がいくつかついています。これは、メジロという鳥が花の蜜を吸った跡なのだとか。

林の近くの芝生には土を掘り起こしたような跡がたくさん。これはモグラ塚と呼ばれるものです。盛り上がった中央の土を動かしてみると、ネズミやハムスターが入れるくらいの穴が空いており、モグラはそこを通れるほどの小さな生き物であることがわかります。

ゴルフ場に「エビフライ」?足元を見たり、枝を見上げたり、身の回りをくまなく散策
続いて一行は松の木の下へ。指導員の方々が「ここにエビフライがあります。探してみましょう!」と声をかけると、「エビフライってなに?」と言いながらも子どもたちは夢中になって探し始めました。

ついに、エビフライを発見! その正体は、リスにかじられた松ぼっくりでした。松ぼっくりの種を食べるためにかじるそうですが、その跡がまるでエビフライのようなかたちになるのです。
松ぼっくりの鱗片は、硬く開いているイメージですが、雨の日は鱗片が湿気を吸って閉じてしまいます。湿気を吸った鱗片は柔らかくなり、簡単に手でちぎることができるため、子どもたちもリスの真似をしてエビフライをつくりました。


次は低木の枝に「むしこぶ」を発見。これは、体長1〜6ミリメートルほどの小さな昆虫「タマバチ」などが枝や葉に卵を産み、植物の組織が変形してこぶ状に大きくなったものです。
低木とはいえ大人でも見上げるところに枝があるため、指導員の方が見やすい場所を探してくれたり、子どもたちで落ちている枝を探したりして「むしこぶ」を一生懸命見つけていました。


そろそろネイチャーウォッチングも終盤。雨の音を楽しみながら出発地点の方へ戻っていると、湖畔にたたずむ一匹の鳥を発見しました。「何の鳥だろう? 羽が濡れていて、クチバシが黄色いね。よく見ると目が緑色をしているよ」という指導員の方の声かけで、子どもたちもじっくりと観察を始めます。

ゲームを楽しみながら自然に触れ、さまざまな発見があったネイチャーウォッチング。このような自然を守り続けるために、私たちはどのようなことを心がけるといいのでしょうか。原田さんは今回のイベントを通して、「体験し、気づきを得ることの大切さ」を伝えたかったといいます。
原田さん
ゴルフ場は、残された里山の自然を守るうえで、とても大きな役割を担っています。これからもこの自然を維持していってほしいです。そのためには、ゴルフ場にはいろいろな自然があることをたくさんの人に知って、身近に感じてもらいたいと思っています。
今回のような自然観察で得られる「気づき」は、身近なところにある自然にも意識を向けさせてくれます。家の近くの公園など、住宅街にも緑はあるので、帰ってから「ここにも自然があったんだ」と気づいてもらえたら嬉しいですね。自然とふれあい、楽しんだという原体験をいっぱい積み上げて、自然とともに生活していくという意識につながっていくことを願っています。

「ゴルフ場の楽しさを多角的に知ってほしい」菊田支配人インタビュー
ゴルフを体験するジュニアレッスン会と、ゴルフ場の自然を観察するネイチャーウォッチングが同時開催されたのは、今回が初めてのこと。どのような目的を持ち、このイベントが企画されたのでしょうか?
菊田支配人
ゴルフ場は普段、ゴルフをプレーする限られた人しか利用しません。そのため当施設では、市民解放日にあわせて無料のイベントを開催することで、近隣に住む市民のみなさんに還元しています。また今回は、ゴルフだけでなく自然にも触れることで、ゴルフ場の楽しさを多角的に知っていただくことを目的としています。

その背景には、「川崎国際生田緑地ゴルフ場」が長年続けてきたサステナブルな取り組みがあったといいます。
菊田支配人
2013年に我われは川崎市から運営管理を受託して以降、環境調査の実施やその結果に基づく中⾧期の維持管理計画の策定、モニタリング実施などの活動を行ってきました。
また、2024年には、有機肥料の使用や計画的な樹木の剪定・伐採など生物多様性に配慮したさまざまな取り組みが認められ、ゴルフ場の先駆けとして「いきもの共生事業所®認証(ABINC)」を取得しています。
環境調査を続けてきたことで、自然環境に変化が現われ、地域と連携した取り組みも広がっていったそうです。
菊田支配人
環境調査は年に1度行われていて、どんな場所にどういう動物がいるか、また生息している動物の増減も調査しています。これにより、タヌキやアライグマが生息しているエリアがわかりましたし、ホトケドジョウという珍しい希少な魚がいることもわかりました。
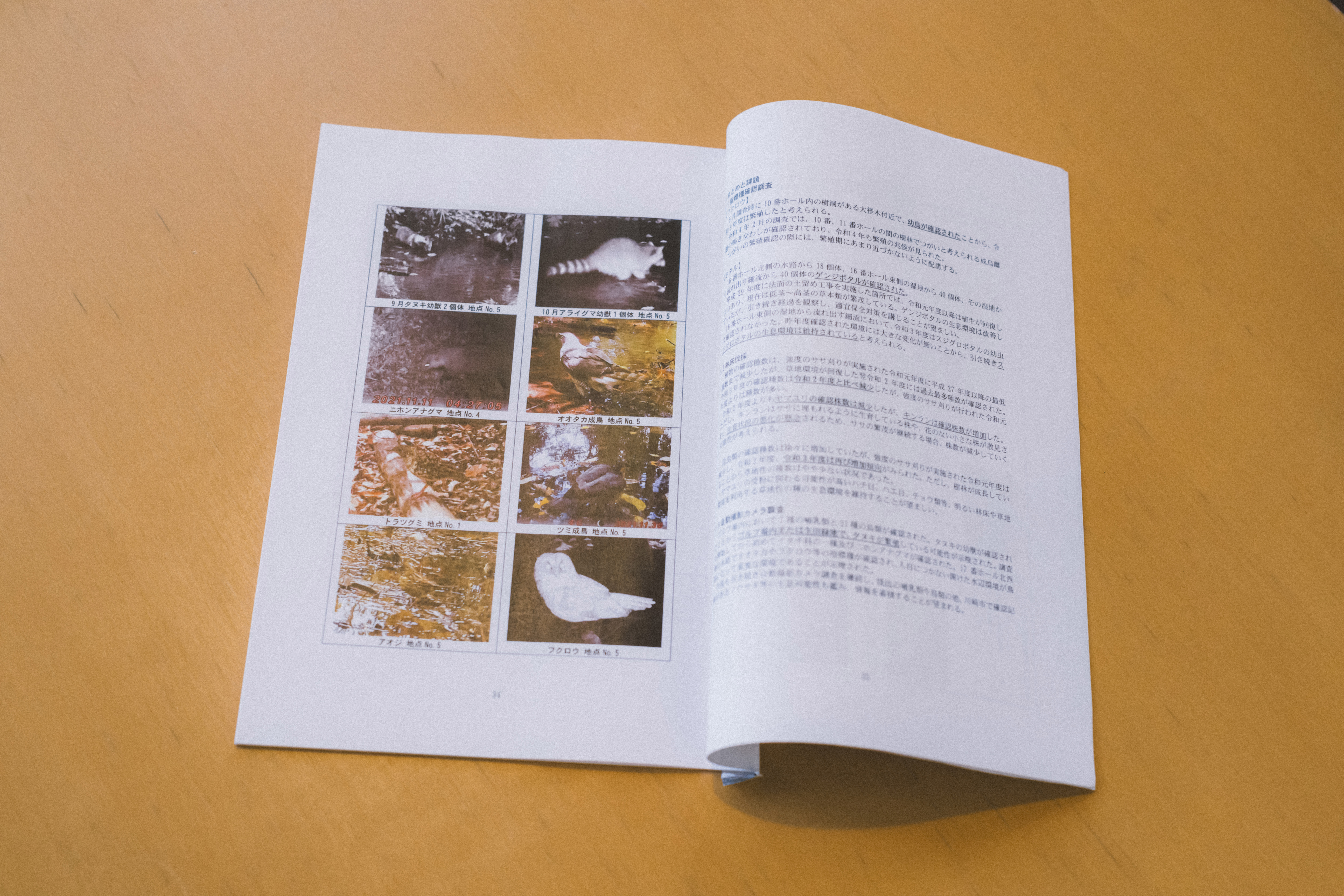
菊田支配人
芝生には環境に配慮し厳しい基準をもとに薬剤を使っています。そのおかげできれいな水質を保ち、ホタルが生息できる環境を守り続けています。また、フクロウなど都心部では珍しい生き物が発見されています。
夏にはこの地域で活動している「飛森谷戸(とんもりやと)の自然を守る会」と夜の自然観察会を実施し、ホタルの幼虫の餌となるカワニナという貝を放流したり、カブトムシやクワガタ探しをしたり、ゴルフ場の芝を裸足で走ったりするなど、ゴルフ場の自然を身近に感じてもらえるようなイベントにつなげています。
最後に、今回のイベントの手応えや、今後チャレンジしたい取り組みについて語ってもらいました。
菊田支配人
自然観察会を冬の日中に開催したのは、今回が初めてです。雨が降る寒い日でしたが、お子さんたちが観察員の皆さんの言葉に耳を傾けたり、手が泥だらけになっても気にせず松ぼっくりを拾って楽しんでいたりする様子を間近で見ることができて、いい会になったと感じました。

菊田支配人
今後も季節や時間帯をずらしてイベントを開催し、子どもや親御さんに、ゴルフ場の中にある自然の多様な姿を知ってもらいたいですね。自然とふれあう体験を通し、ゴルフ場のように人の手が入ることは、自然を守ることに寄与していることを伝え、日頃から生き物と共生する意識へつなげてほしいと思います。

ゴルフ場の自然を楽しむことが、自然環境を守り続けることにつながる
今回のイベントを体験した子どもたちからは、「エビフライ探しが楽しかった」「むしこぶとか、知らないことを知れて面白かった」「松ぼっくりを家に持ち帰って、乾いたらどうなるか見てみたいな」「いろんな鳥の鳴き声を聴けて楽しかったから、家の近くではどんな鳥の鳴き声が聴こえるか聴いてみたい」との声が聞けました。
ネイチャーウォッチングのあとは、スナッグゴルフ形式でレッスンが行われ、ゴルフの基本を楽しく学んだ子どもたち。自然とスポーツ、両方の側面からゴルフ場の魅力に触れられたイベントとなりました。

盛況のうちに終了した今回のイベント。スポーツを楽しむことを目的に参加した方々も、ネイチャーウォッチングを通して、ゴルフ場には豊かな自然が育まれ、生き物と人が共生できるしくみが「創造」されていることを実感できたようです。身近な自然環境について五感を働かせながら学び、自然環境への意識を高めていく東急不動産ホールディングスの取り組みは、これからも続いていきます。
記事をシェアする














